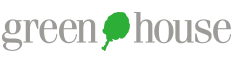成分名 オーラバリア ®
オーラバリアとは、口内環境の改善を目的として開発された森永乳業独自の機能性素材で、臭いの発生源である悪玉菌の増殖を抑えることが研究で確認されており、オーラルフレイル進行を抑える効果も期待されています。
| 学名 | Lactoferin and lactoperpxidase |
|---|---|
| 和名 | オーラバリア ® |
| 英名 | Orabarrier |

●この成分ページを書いた人●
グリーンハウス株式会社
代表取締役 横尾一浩医師や専門家の方々と口臭について意見を交わし、15年以上に亘り数多くの口臭対策商品をつくってきました。その経験の中で得た口臭に関する幅広い知識を、読者の皆さんのために余すことなくお伝えいたします。
目次
1.オーラバリア ® とは
オーラバリア ® とは、口内環境の改善を目的として開発された森永乳業独自の機能性素材で、特許(第4203120号)を取得しています。口腔内の口臭・歯周病の抑制を目的とするオーラバリア ® は、ラクトフェリンとラクトパーオキシダーゼという2つの原料を組み合わせて開発されました。
ラクトフェリンは乳たんぱく質の一種で、哺乳類の乳や唾液中に含まれています。
生まれたばかりの人間の赤ちゃんは、まだ体力が備わっておらず、免疫力もありません。そんな状態の赤ちゃんを、感染症から守る働きがラクトフェリンにあることが知られており、実際に新生児に与える初乳にはラクトフェリンが多く含まれ、産後数週間の母乳と比べても約3倍もの量です。
同じく乳や唾液中に含まれているラクトパーオキシダーゼは、それ自身に殺菌作用はありません。
しかし、汗や唾液などの外分泌液に含まれる酵素であることから、唾液中のチオシアン酸イオンと過酸化水素に反応することで抗菌活性の高い成分を作り出し、菌の増殖を抑えます。
これら2つの抗菌成分を掛け合わせたオーラバリア ® には、オーラルフレイル進行を抑える効果が期待されています。
オーラルフレイルは近年、厚生労働科学研究で提唱された、「身体の老い」に対する新しい概念で、滑舌の低下や食べこぼし、口の乾燥など口内機能の衰えることを指し、早期の重要な老化のサインとされています。特に高齢者は、自浄作用を持つ唾液の分泌量が低下することで細菌が増殖し、歯周病を引き起こすリスクが高まるので注意が必要です。
これに対し、オーラバリア ® は口臭抑制や抗菌作用などの働きによって口内環境の健康を保ちます。
従来の口臭抑制素材は、一時的に香りで臭いを覆うマスキングが主流でしたが、オーラバリア ® は臭いの発生源である悪玉菌の増殖を抑えることが研究で確認されています。
2.オーラバリア ® の機能性
2-1.口臭抑制作用
口腔内で発生する口臭の主な原因の1つが、悪玉菌といわれています。
口内に残っている食べ物のカスや舌苔のタンパク質を餌に、虫歯や歯周病の原因となる悪玉菌がどんどん増殖しますが、この悪玉菌が生み出す酵素が食物のカスに含まれるタンパク質を分解することで、悪臭成分が発生し口臭が生まれます。
オーラバリア ® はこの酵素の働きを抑える作用を持ちます。およそ2000種類ある酵素は、体のあらゆる器官に存在し、それぞれが異なる機能で各器官に適した働きをしています。体内では、常に様々な物質の分解・合成が行われており、これらの生体反応も、酵素の働きでスムーズに行われます。
また、オーラバリア ® は口臭産生に関わる悪玉菌の酵素の働きだけを阻害し直接不活性化させることで、口臭の発生自体を抑えます。実際、酵素阻害作用を調べた実験では、作用前に比べ作用10分後には活性率が80%も急激に下がったことが分かっています。(※1)
その後の研究で、さらなる作用機構も明らかになってきました。オーラバリア ® のラクトパーオキシダーゼが、チオシアン酸イオンと過酸化水素に反応することで、次亜チオシアン酸を生み出します。この次亜チオシアン酸が酵素リアーゼの働きを直接抑えることで、口臭抑制につながったことも確認されています。
口腔内で発生する口臭原因として見落とされがちなのが舌苔です。舌苔は、食べ物の残りカスや古くなった口腔内の粘膜が舌の表面に付いた状態で、舌が白いのは舌苔が蓄積されている証拠です。
舌のクリーニングをすることで口臭が大きく減少することも確認されており、悪臭が発生しやすい場所です。この舌苔を調べて歯周病菌フソバクテリウム・ヌクレアタムを保有していた11名がオーラバリア ® を摂取した結果、摂取前と比べて歯周病菌が有意に減少しました。(※2)
参考※1

参考※2

2-2.抗菌活性(歯周病菌の抑制)
口腔内には数百種類におよぶ細菌が生息しており、その数は腸内細菌に匹敵するほどです。
腸内細菌が腸内で小さな集合体をつくる様子が花畑に見えることから、腸内フローラと呼ばれますが、口腔内の細菌の集まりも口内フローラといいます。
口内フローラに潜在する細菌は、口からのウイルス侵入を防ぐなどの体に良い働きをする細菌と、歯周病菌などの体に悪影響を与える細菌の2つに大きく分けられます。
体に悪い働きをする細菌の増殖は、口内フローラのバランスを崩し、歯周病等の口内のトラブルを引き起こすリスクを高めます。さらに、近年のオーラルフレイルに関する様々な研究から、例えば糖尿病や胃がんなどの全身への健康被害も口腔問題が原因だと考えられるようになってきました。
その中でも歯周病菌は、唾液の分泌量が少ないことや、歯茎からの出血によって一気に増殖して影響力を強めます。
オーラバリア ® は口腔内の衛生状態に悪影響を与える細菌を減少させ、口腔内の健康を保つ働きをする細菌を増加させることで、口内フローラのバランスを改善します。
歯周病菌約1000万個に対して8mg/mlのオーラバリア ® を加えて検証した結果、5分後には歯周病菌は約1万個、10分後には500個になり、大幅な減少がみられました。(※3)
また、オーラバリア ® に含まれるラクトフェリンは、鉄と結合しやすい糖たんぱく質です。鉄分を栄養にして増殖する性質を持つ歯周病菌よりも先に、ラクトフェリンと鉄が結合することによって、歯周病菌は鉄不足に陥り力を弱めます。
参考※3

2-3.揮発性硫黄化合物抑制作用
口腔内細菌の働きによって生成される悪臭成分のほとんどは、揮発性硫黄化合物です。
揮発性硫黄化合物とは口臭の主要なガス成分であり、代表的なものとして、卵が腐ったような臭いを放つ硫黄水素や、キャベツが腐ったような臭いを放つジメチルサルファイド、同じく玉ねぎが腐った臭いを放つメチルメルカプタンなどがあります。
この中で、最も臭気が強いのがメチルメルカプタンです。
歯の周りの組織に炎症が起きることで、歯茎から膿が出ることがありますが、この膿の中にも悪臭成分メチルメルカプタンは含まれており、悪臭を発生させるだけでなく、歯周病の進行を助長する物質です。
口臭をもつ4名が、1時間おきにオーラバリア ® を摂取し口臭の変化を調べた結果、口臭測定器ではすぐに悪臭を感じないレベルにまで臭いは抑えられ、悪臭成分メチルメルカプタンの減少も確認することができました。(※4)
参考※4

3.機能性を裏付ける豊富な研究と安全性
| 題名 | 掲載 | 発行日 |
|---|---|---|
| ファクトフェリン+ラクトパーオキシダーゼ配合錠菓の口臭抑制効果と唾液中細菌に対する影響 | Clin Oral invest | 2011 |
| ラクトフェリン+ラクトパーオキシダーゼ配合錠菓摂取による歯周炎への影響 | ラクトフェリン | 2011 |
| 歯周病患者におけるラクトフェリン+ラクトパーオキシダーゼ錠菓摂取による体感効果 | 歯科東洋医誌 | 2011 |
| ラクトフェリン+ラクトパーオキシダーゼ含有粉末組成物の抗菌作用および口臭抑制作用 | 日本農芸化学会 | 2014 |
| オーラバリア ®(ラクトフェリン+ラクトパーオキシダーゼ)配合食品の口腔衛生改善効果 | 日本老年歯科医学会 | 2014 |
| 乳タンパク質ラクトフェリン+ラクトパーオキシダーゼの口腔衛生分野への応用 | 日本酪農学会奨励賞 | 2015 |
4.市販サプリメントを購入する際の注意点
オーラバリア ® は口腔内の悪臭成分に素早く働きかけ臭いを抑制するとともに、オーラルフレイル予防に役立つ注目素材です。オーラバリア ® を含むサプリは、牛乳由来の成分が含まれるので、乳アレルギーの方は摂取を控えてください。
また、販売中のサプリのほとんどが舐めるタイプのため、香料や甘味料が含まれていることがあります。商品を比較し、または口コミなどを参考にしながら自分に合ったサプリを選びましょう。
オーラバリア ® 配合商品一覧
※2021年4月現在調べ
オーラルデント

【内容量】30粒
【一日目安量】1粒
オーラケア

【内容量】20粒
【一日目安量】2粒
オーラバリア

【内容量】30粒
【一日目安量】1粒
アロマタブレット365

【内容量】30粒
【一日目安量】1粒
マスクプラス

【内容量】17粒
【一日目安量】2粒
口臭・口内ケアタブレット オーラバリア

【内容量】18粒
【一日目安量】3粒
オーラスマイル

【内容量】30粒
【一日目安量】2粒
オーラバリア

【内容量】30粒
【一日目安量】2粒
参照元
1)オーラバリア ® ,森永乳業,2021年閲覧
2)ラクトフェリン,ニプロ株式会社,2021年閲覧
3)ラクトフェリンが歯周病を抑制!?唾液が口内環境を整える!,Club Sunstar,2021年閲覧
4)口腔衛生素材オーラバリア ® (ラクトフェリン++ラクトパーオキシダーゼ)の研究開発,NEWS RELEASE 森永乳業株式会社,2014年
5) 「口臭の原因物質である硫化水素」を産生する酵素の立体構造と反応機構を解明,構造生物薬学,2018年
6)「森永オーラバリア ® 」,NEWS RELEASE 森永乳業株式会社,2014年
7)希少糖によるラクトパーオキシダーゼの阻害と利用,バイオサイエンスデータベースセンター,2008年
8)ラクトフェリンについて,株式会社NRLファーマ,2021年閲覧
9)口臭の原因,赤坂見附歯科,2021年閲覧
10)歯周病由来の口臭とメチルメルカプタンの有害性,東京国際クリニック,2021年
11)口内フローラについて,医療法人のはら歯科クリニック,2021年閲覧